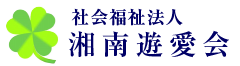雪の予報でしたが、横浜は久しぶりに冷たい雨が降りました。
さて、2月2日、ゆうあいの郷の昼食は、行事食の日でした。行事食のテーマはもちろん ”節分”です。
数日前から職員が作った飾り、利用者の皆様の塗り絵を、フロアに飾りつけをしたり、職員がレクリエーシ
ョンで、鬼のお面をかぶったりして節分を楽しみました。






節分は2月3日のイメージが強いですが、皆様知っての通り、今年は、平年より1日早い2月2日であり
ました。そもそも節分とは、中国で発祥した暦法「二十四節気(にじゅうしせっき)」に由来するもので、
もともと「立春、立夏、立秋、立冬」の各前日が節分とされていました。しかしながら今では、「立春」の
前日のみが定着しました。 なお立春の日を定めているのは国立天文台であります。

地球が太陽を1周する時間(公転)は365日ぴったりではなく、”365日+6時間弱”で、6時間につい
ては、4年に1度のうるう年で調整しますが、”弱”については調整できず、年々少しずつずれてしまい、立春
も年によって変動し、それに伴い節分の日も変動するとのことです。(詳しいことは皆様お調べ下さいね)
ちなみに、2021~2057年の期間では、4年ごとに節分の日が2月2日に切り替わるほか、198
4年は2月4日が節分の日でした。
節分では、豆まきが定番ですよね。邪気や厄の象徴である鬼は、形の見えない災害、病、飢饉などの恐ろ
しい出来事を引き起こすと考えられていたそうで、鬼を追い払うため、五穀のひとつで、穀霊が宿るとされ
る、大豆をまいて鬼を払うとのこと。また、「豆を炒る」ことが「魔目を射る」に通じて「魔滅(まめ)」と
なるため、煎った大豆を使うとのことです。
また、鬼は真夜中にやってくるとされ、豆まきは夜に行い、窓を開け「鬼は外!」と大きな声で唱えなが
ら外に向かって豆をまき、鬼が戻ってこないように、すぐに窓を閉めて「福は内!」と、室内に豆をまきま
す。家の奥から順番に、最後は玄関までまいて、家中の鬼を追い払うのが豆まきの一般的なルールだそうで
す。ちなみに、渡辺綱(わたなべつな)という平安時代の武将が鬼を退治したことから、“ワタナベ”という
姓をもつ人は、鬼に恐れられており、”豆まきはしなくてもいい”とされています。(私のことです)


最近、豆まきは後片付けが大変という理由や、TVの宣伝効果で、恵方巻を食べる家庭が多いと聞きま
す。恵方巻きは、1989年に、某コンビニエンスチェーンが、広島県で太巻きを「恵方巻き」と名前をつ
けて販売を始めました。元々は、江戸時代から明治時代にかけ、大阪の花街で節分をお祝いしたり、商売繁
盛を祈ったりしたときに食べる、「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」がルーツと言われています。
恵方巻は、その年の恵方(2025年は西南西)を向き、願い事をしながら無言で一気に食べるのがルー
ルで、巻き寿司を切らずに一本丸ごと食べるのは、「縁を切らない」という意味が込められています。その
ほか七福神にちなんで、7種類の具材が入れられ、「福を巻き込む」という願いが込められています。
またまた、節分に関連するお話しが長くなりましたが、昼食のメニュー紹介です。




今回のメニューは、節分にちなんだ食材で構成されています。
まずは豆につきましては、鬼を退治するために、季節の変わり目である節分に、霊力がやどるとされてい
る大豆を食べるんだそうです。更に、鬼が嫌いなイワシを食べるのが良いとされています。
鬼は、イワシの生臭さやイワシを焼いた時に出る煙が大嫌いなのだそうです。また、節分ではイワシを飾る
習慣もあり、「柊鰯」といわれ、柊の小枝に焼いたイワシの頭を突き刺したものを、戸口に飾るというもの
です。柊も尖った部分が目を突き刺すと言われるため、鬼の苦手なものの1つなのです。
本日の行事食のメニューでは特に、えびがたくさん入った、色彩の豊かな、ちらし寿司が好評でした。